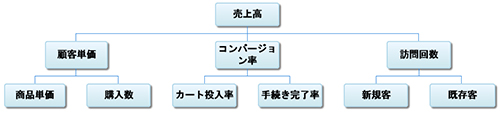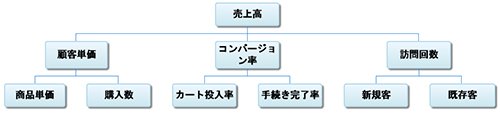以前、金融庁が金融機関の評価にベンチマークを取り入れるという内容をお伝えしました。そのベンチマークが9月に公表されておりますので、ここで改めてお伝えいたします。
まず、ベンチマーク策定の趣旨です(ベンチマーク策定の趣旨より一部抜粋。全文はこちら→「金融仲介機能のベンチマークについて」
|
多くの金融機関は、その経営理念や事業戦略等において、金融仲介機能を発揮し、取引先企業のニーズや課題に応じた融資やソリューション(解決策)の提供等を行うことにより、取引先企業の成長や地域経済の活性化等に貢献していく方針を掲げている。 他方、企業からは、「金融機関は、相変わらず担保・保証に依存しているなど対応は変わっていない」といった声が依然として聞かれる。昨事務年度に実施した企業ヒアリングでは、多くの企業が、金融機関に対して、事業の理解に基づく融資や経営改善等に向けた支援を求めていることが明らかとなった。 |
つまり、金融機関が掲げている方針と事業の実態が異なるので、金融庁が評価のためのベンチマークを公表しますとのこと。
そして、ベンチマークの活用として、以下の三点を掲げています。
(1)自己点検・評価
(2)自主的開示
(3)対話の実施
このうち、(1)については金融機関の、(3)については金融庁と金融機関の点についてなので省きますが、(2)については、以下のように記載されています。
|
企業にとっては、自らのニーズや課題解決に応えてくれる金融機関を主体的に選択できるための十分な情報が提供されることが重要であり、金融機関においては、ベンチマークを用い、自身の金融仲介の取組みを積極的かつ具体的に開示し、企業との間の情報の非対称性の解消に努めていただきたい。 |
つまり、金融機関はベンチマークによって自らの取り組みを開示してね!という訳です。これが開示されると何が変わるかというと、中小企業が金融機関を評価できるということです。
いままでは金融機関が中小企業を一方的に評価して、融資条件等を決めていました。そのため、そこには情報の非対称性がありました。しかし、これが公表されることにより、「隣の銀行の方が、しっかりサポートしてくれているではないか!」と分かれば、中小企業がメインバンクを変える行動につながります。
ベンチマークの開示については、まだまだ先で、どのようになるかは分かりません。しかし、スコアが良い金融機関ほど積極的に開示していくでしょうから、金融機関間での競争につながり、中小企業にとっても良い結果につながるかもしれません。
最後に、本題のベンチマークの内容です。ベンチマークは【共通ベンチマーク】として5項目、【選択ベンチマーク】として50項目が掲げられています。さすがにこれを全部ご説明する訳にはいきませんので、気になる方はご自身で目を通していただくとして、今回は一部を取り上げさせていただきます。(全てのベンチマークはこちら→「金融仲介機能のベンチマーク」
中小企業における融資において特に気にすべき点は、選択ベンチマークのうち、下記の部分です。
|
(2)事業性評価に基づく融資等、担保・保証に過度に依存しない融資 |
5.事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して対話を行っている取引先数、及び、左記のうち、労働生産性向上のための対話を行っている取引先数 |
|---|---|
|
6.事業性評価に基づく融資を行っている与信先の融資金利と全融資金利との差 |
|
|
7.地元の中小企業与信先のうち、無担保与信先数、及び、無担保融資額の割合(先数単体ベース) |
|
|
8.地元の中小企業与信先のうち、根抵当権を設定していない与信先の割合(先数単体ベース) |
|
|
9.地元の中小企業与信先のうち、無保証のメイン取引先の割合(先数単体ベース) |
|
|
10.中小企業向け融資のうち、信用保証協会保証付き融資額の割合、及び、100%保証付き融資額の割合 |
|
|
11.経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及び、全与信先数に占める割合(先数単体ベース) |
つまり、融資の際の担保や保証に関する部分です。金融機関においては、当然のように物的担保を要求し、人的担保である経営者保証に関しては神聖不可侵の領域だというスタンスです。
しかし、以前にもお伝えしたように、担保や経営者保証が外れている中小企業も増えてきました。これは、業績の良し悪しにも影響しますが、やはり金融機関ときちんと対話をしているかどうかにも影響があります。
この対話というのは幅広い意味です。例えば、試算表や決算書を渡して説明するだけではなく、自社の事業を理解してもらえるようビジネスモデルを説明したり、成長可能性や経営課題を伝えて支援を求めたりといったようなことです。
ちなみに、金融機関同士を競合させるだけでも経営者保証が外れることがあります。経営者保証を外すことを嫌がるのは、既存の借入先です。営業に来た新規の金融機関に打診を行えば、意外と経営者保証無しで融資を引き受けてくれる場合もあります。一行でも経営者保証無しの融資が実現すれば、借入金における金融機関別のシェアを変動させていき、最終的に経営者保証無しの状態に仕上げるという戦略も可能です。
そして、今後、この点がベンチマークのスコアにも影響してくるのです。
「おたくの銀行は、担保や経営者保証に関するベンチマークはどのようにお考えですか?」と、担当者を牽制し始める日も遠くないかもしれません。
しかし、同時に中小企業においても求められる点が出てきます。それが、金融機関の事業性評価に対する、経営者からの開示姿勢です。
担保も無し、経営者保証も無しで金融機関が融資を行うのであれば、決算書などの財務面だけではなく、対象企業の事業を評価する必要があります。上記でお伝えしたように、非財務面である事業内容や成長性、経営者の性格、経営課題などを評価し、融資の可否や条件を決めていくことになります。
例えば、融資を引き出すことが上手な経営者は、決算書を渡すだけではなく、今後の自社の成長可能性について、経営計画と題してプレゼン資料を作成します。これは結果として、事業性評価をしてもらうための情報を金融機関に開示していることになります。
もちろん、金融機関に対してプレゼンをしてくださいとお伝えしている訳ではありません。ただ、担保や経営者保証を外していく選択肢というのは、今まで以上に重要になってきます。その際に、金融機関に行ってもらうべきは事業性評価であり、そのためには自社の過去の結果である財務よりも、現在や将来に向けての説明が重要になってくるということです。
いままで、金融機関と中小企業の関係というのは、どちらかというと一方的なものでした。つまり、金融機関が圧倒的に上から目線か、中小企業が金融機関を顎で使うか(格付けが上位の企業がですが…)の分かりやすい関係性です。
この関係性を、事業性評価の名のもとに、自社の情報を金融機関に共有するような形で対等な位置付けに持っていきます。当然狙うポイントは、融資条件の緩和です。
これに応じられないような金融機関は、結果として評価を落としていくことにつながるため、中小企業の市場から淘汰される可能性もあります。地方銀行がこの波をまともに受けたら、単独で生き残っていくことが難しくなります。つまり、中小企業から支持される有力地方銀行に吸収されていくことになります。
以上から、皆さまの会社が、金融機関に事業性評価を求めた場合の反応が、今後のメインバンクの選定にも影響してくるということが分かります。
現時点では、このベンチマークの影響が、地方銀行のさらに地方の支店にまで波及しているとは思えませんが、これから数年という期間においては徐々に浸透してくるのではないかと考えます。
今後も金融機関からの融資が欠かせないという企業においては、金融庁がベンチマークを発表した趣旨を理解し、金融機関の動向を踏まえて対応していくことが望ましいでしょう。