もちろん、法人の税務調査のお話。
国税庁から、平成21年度の法人税等の調査実績が公表されました。
過去20年間で、二番目に多い申告もれ所得金額です。
その額は、なんと2兆493億円!
平成20年度の申告もれ所得金額は、1兆3,255億円と過去20年間で最低でした。
これはサブプライム問題から端を発したリーマンショック前後までの期間と重なるので、当然と言えば当然かもしれません。
ちなみに、平成21年度の調査件数は、前年よりも4.5%低い13万9千件(法人数全体の約5.3%)。
これは、国税庁の下記アナウンスから意図が読み取れます。
「平成21事務年度における法人税等の調査については、大口・悪質な不正計算が想定される事案に加え、社会・経済情勢の変化を踏まえつつ、無申告法人、海外取引法人、公益法人等をはじめとする波及効果の高い事案に取り組みました」
“取れるところから取る!”
国税庁は選択と集中により、効率の良い調査を行ったという事になります。
そして、気になる点は、法人全体の申告所得もれの対前年増加額が7,238億円であるのに対し、資本金1億円以上の法人(以下、「大企業」)の申告所得もれの対前年増加額は7,555億円だったという事です。
つまり、資本金1億円未満の法人(以下、「中小企業」)の調査においては、過去最低であった平成20年度よりも、更に申告もれ所得金額が減少しました。
また、平成21年度の赤字企業の割合は74.5%で、平成20年度の71%(平成19年度67%)より悪化しています。
という事は、中小企業の調査でも・・・
“取れるところから取る!”
という事になります。
当然、企業努力により黒字を確保している中小企業は、税務調査の頻度が多くなるのは間違いありません。
「ご注意ください!」
というのもおかしな話ですが、
実際、セカンドオピニオンで、黒字企業の税務調査でのご相談が非常に増えています。
税務調査一発でガタつく企業も意外と多く、その後に税理士と仲違いされます。
「何もやましい事はない!」
という経営者の方でも、“税務調査”と聞くと、一瞬ギクッとなるのは人の理・・・。
しかも、税理士による確認もれや判断ミスは、企業側ではどうにもなりません。
これは、近年、企業取引が非常に複雑化しているにもかかわらず、年配の税理士や経験が浅い税理士が、企業の動きについて行けないという事を意味しています。
セカンドオピニオンでご相談が多いのも、このような税理士が顧問の企業様です。
とはいえ、税務調査を怖がる必要は一切ありません。
また、怖がるよりも積極的に税務上の守りを固めてください。
積極的にというのは、保守的な税理士が好きな“無難すぎる”守りではなく、税制上の制度を使い倒して、無駄な税金を払わなくするという事です。
増税に、減税・・・。
廃止された税制に、新しく始まる税制・・・。
グループ法人税制という、関連会社がある企業は見逃せない制度も始まりました。
民主党政権になって、企業を取り巻く税制も大混乱する気配が漂いますが、この大混乱に巻き込まれてしまっては、無駄なエネルギーを使わせられるだけ。
一部の業界では景気の回復傾向も見られますが、補助金を含め税制上の恩恵が消えた瞬間に流れは変わるかもしれません。
さあ、今年よりも更に荒れそうな平成23年度の開始は目の前に来ています。
攻めも守りもスタートダッシュが成功するかは、年末年始の一番頭が切り替わる時期の判断に掛っているのではないでしょうか。
体は休めても、頭はフル回転の年末年始を迎えましょう。
月: 2013年2月
移動年計の効用
先般、お客様から、既存客数や既存客売上高が
低下しているという相談がありました。
そして、過去3年間の既存客数などの統計を頂きました。
確かに、頂いた数値を検証していると、
数値は低下傾向にあるように思えましたが、
私は、移動年計のグラフを項目ごとに作るようにお願いしました。
移動年計については、過去の私の本で説明していますし、
今度ダイヤモンド社から出版される本でも詳しく解説をしていますので参照いただければと思いますが、
簡単に言ってしまうと、
毎日または毎月、1年間の売上げや顧客数を見ていく方法です。
たとえば、
2010年11月の数値を見るとすると
一般的には、11月単月の数値や期首から11月までの累計の数値を計測するのが一般的です。
移動年計では、「年計」というように、
2009年12月から2010年11月の合計の数値を見ていきます。
つまり、決算書の売上高の数値を毎月見ていくわけです。
こうすると、季節要因などが排除できて、
長期的な傾向が見えてきます。
また、2年合計を半分に割って、
1年合計と比較することで、
短期、長期の傾向値比較も可能です。
毎月、1年間の合計を集計していくということは、
それほど数値に大きな変動がないように
思うかもしれませんが、
実際は、かなり大きく揺れるのが一般的です。
つまり、その「揺れ」が
分析に値する事象です。
相談いただいた方の年計グラフを見ていても、
グラフが低下トレンドになる時と
上昇トレンドになる時が
明確に分かれていました。
毎月の一年計を出しているだけなのですが、
こうした傾向が現れるのが中小企業です。
つまり、
企業のちょっとした動きの違いが
敏感に繁栄されているのです。
そして、
それぞれのトレンドについて
その時何があったかを追いかけていきます。
こうすることで、
意外な発見があります。
ぜひとも試してみてください。
2010年も、もう少しで終わります。
小売業の方々は、これからクリスマス、年末商戦。
特に、インターネットでは、
年々、クリスマス商戦が盛り上がっていますので、
息の抜けないところです。
小売業や飲食業以外の方々は、
そろそろ来年の戦術などの整理の時期だと思いますので、
年末にでも、年計分析を実行してみてください。
もちろん、年末が忙しい小売業などの方々は、
商戦が終わった以後にぜひとも実行してみてください。
会計は、思想である
ダイヤモンド社から2011年9月に出版した本は、久しぶりに会計の本です。
この本では、最後の章で、小さな架空の物語を書きました。
会計を知らない家族が、ビジネスをはじめ、ライバルの出現と共に会計に翻弄されていくお話です。
この架空の物語で、何を明らかにしようとしたかを一言で言えば、経営には、思想が必要だということかもしれません。
そして、経営に必要な思想はいろいろあるけれど、会計も思想であると言いたかったように思います。
実際、この本の第二章では、思想としての会計をテーマにしています。
そして、次のような文章ではじめています。
******************************
第二章は、一般的な会計の本の文脈から考えると少し特殊なトーンが
あるもしれません。
なぜならば、これから「会計」という道具を使う「思想」について考えて
いこうとしているからです。
そして、会計を利用するひとつの「思想」から会計とは何かを明らかに
してみようと思います。
会計の思想を語るというのは少し生意気かもしれません。ここで言う
「思想」は会計専門の学者や官僚が法律などを策定するときに拠り
どころとするようなものではありません。
中小企業経営者が、会計という道具を利用する際に必要な「思想」です。
「思想」などと大上段に構えることなく、単に「アイデア」と言い切ることも
できないこともありませんが、あくまでも「アイデア」とは違います。
ひとつの「思想」というものは、誰もが受け入れられるものではありません。
また、思考に飛躍がある可能性もあります。しかし、現在の中小企業の
会計に足りないものは「思想」だと思うのです。「思想」がないために、
混乱しているのです。
企業経営を上手に運営している経営者には、思想があります。通常、
そうした経営者の経営における思想は巷間に多く流布していますが、
彼らには会計に対しても思想があります。そうしたことを明らかにし
ながら、目指すべき会計=思想を考えていきます。
******************************
この考えは大きな分岐点になります。
会計を単なる技術と考えている限り、会計は武器になることはありません。
もちろん、多少はなるでしょうが、限界があるのです。
会計の専門家が、時折、おかしなアドバイスをしてしまうのは、彼らが教科書通りのことをするからです。
つまり、技術としての会計に焦点を当ててしまうところに、失敗があります。
しかし、会計を思想と考えてみると、まったく違う世界が現れます。そして、いろいろな数値管理の手法が浮かんできます。
経営に占める会計の役割は数パーセントとおっしゃる方もいますが、それは大きく間違っています。
そういう方は、単なる技術としての会計について言っている。つまり、会計が何かをわかっていないのです。おそらく、会計は分析レベルのものと思っているのです。
しかし、思想としての会計を考えるならば、その位置づけは、40%以上は占める重要なものに変わってきます。
思想としての会計を考える時、別に私の新著を読んでいただく必要はありません。
自分は、どういう数字にしたいのか・・が明確ならば、それはもう思想です。
それを単なる希望とか目標と思うからいけないのです。
ちょっとした言葉の違いですが、このちょっとした言葉の違いはとても大きいと思います。
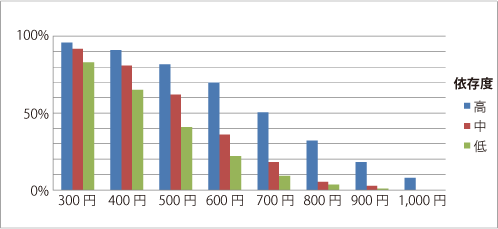
タバコ増税にみる参照価格
「いっそのこと、1,000円になれば禁煙するのに・・・」
喫煙者から良く聞こえてくるセリフです。
10月1日、タバコ税の引き上げにともない、タバコの値段が上がりました。
過去10年間で、3度の増税がありましたが、いずれも値上げとして反映されたのは20円程度。
今回のように100円以上の値上げは初めてのことで、業界関係者の不安は募る一方です・・・。
タバコの値段と禁煙意思との関係について、京都大学の依田教授が興味深い研究を行っています。
2007年に発表された『禁煙意思に関するコンジョイント分析』は、今回の値上げに際し、政府税調も参考にしたとか、してないとか。
調査に際し、研究チームは喫煙者に「タバコの価格がいくらになったら禁煙しますか?」というアンケートを実施しました。
結果はつぎのとおりです。

縦軸は喫煙継続率、つまり、「その値段になってもタバコを吸います。」という数値です。また、3本のグラフは回答者のニコチン依存度を示し、依存度別に価格と禁煙意思の相関関係を測っています。
当時の価格300円でも継続率が100%を下回っているのは、「価格が変わらなくても、いつでも止めたいと思っている・・・」という意思の表れです。
お決まりのセリフ、「いっそのこと、1,000円になれば・・・」を検証してみると、確かに1,000円になれば、依存度にかかわらず、ほぼすべての人が禁煙を試みるようです。
さて、今回の値上げ水準である400円を見てみましょう。
依存度の高い人の約10%、中位の人の約20%、低い人の約35%がタバコをやめようとします。
実際には喫煙者のニコチン依存度が平均的に分布しているわけではない、という前提はありますが、仮に単純平均してみると、全体の22%、およそ5人に1人がタバコをやめようとするはずです。
・・・でも、あれ?皆さんも周りを見渡してみて下さい。5人に1人もいますか?タバコをやめようとした人。
ニコチンには依存性がありますので、実際に禁煙した、ではなく、禁煙を試みた、で構いません。それでも私の実感としては、10人に1人いるかどうか・・・。
京都大学の研究結果とのズレはどこから生まれたのでしょうか?
違いは、今回の値上げについて、いくらを『参照点』として認識しているか、というところにあります。
消費者はモノの価格を判断する際に、基準となる『参照点』からの距離で価格の良し悪しを判断しています。
そのモノがもたらす有用性・経済的価値を冷静に判断し、0地点から価格を判断することなんてあり得ません。
京都大学の研究において、対象者は、当時の価格300円を基準に価格を判断しました。
今回の値上げでも、300円を基準に判断したはず・・・、なのですが、値上げに至るまでのノイズがかなりありました。
平成22年度税制改正に向けて、当時の長妻厚労相はテレビ放送で「600円をめどに」とコメントしていましたし、他の方面からは「欧米並みの1,000円を基準に」との声もありました。
喫煙者は無意識的に、これらの高価格帯を一度は覚悟したはずです。
それを基準にすれば、今回の400円なんてたいしたことはありません。
・・・少し気になりませんか?
そういった雑音が自然発生的に起こったものなのか、意図的に起こされたものなのか。
政府は、今回の値上げについて「国民の健康増進のため」との御旗を掲げていますが、税収が厳しいのは周知のとおり。ホンネを言ってしまえば、税収を確保したかったはずです。
(ちなみに依田教授の研究によると、タバコ税の増加と、喫煙者の減少により、タバコ税収自体が減少に転じるクロスポイントは600円と予測されています。)
また、JTにしても、
「値上げ反対!400円反対!」と言って400円に落ち着くよりも、
「値上げ反対!1,000円反対!」と言って400円に落ちついた方がいいわけです。
・・・真偽のほどはわかりませんが、・・・こういったノイズ、いろいろなところで使えますよね。
税法だけで考えるのは止めよう
先般、当社のコンサルティングのお客様に
税務調査が入りました。
そして、ある処理が不正と判断され、
3000万円ほどの納税を請求されました。
そして、その方の顧問税理士も、
税務署同様、処理の間違いを認めて
払うべきだと主張。
そのお客様は、納得できず、
当社の『財務プライベート・コンセント』という
税理士セカンドオピニオンのサービスを使い
相談にきました。
その方の話を聞いて
私が出した結論は、
税務署の言うことは聞く必要がない。
こちらの主張を言い切るべきということでした。
そして、
どのような主張をするべきかを
伝授しました。
結果は、納税の必要なし。
こちらの意見が無事通りました。
その方の顧問税理士さんに対する
不信を残して、税務調査は無事終了しました。
さて、この取引の認定では何に問題があったのでしょう?
それを一言で言うと、
税務署と顧問税理士さんは、税務だけから考え、
私は、税務で考えず、
民法で考えた。これだけです。
取引を、民法の原則で
俯瞰すれば、その目的も形態も明かで、
課税になる要件など最初からどこにもなかったのです。
その「最初からどこにもなかった事象」に3000万円の
納付を要求してきたのです。
それも、悪気があったわけではありません。
なぜならば、顧問税理士さんもその意見を受け入れたのですから・・・・。
しかし、
誠実に、税法だけを見て判断した・・というのでは困ります。
税務の現場では、時々、こうした税法の拡大解釈が起こります。
そして、それを阻止すべき税理士さんも民法をご存じでないと
税務署の言い分が正しいと判断してしまうようです。
私たちが毎日行う取引は、
民法、商法に基づいて行っていることになっています。
もちろん、そんなことを気にする人はいません。
こうした法律は、争いになったときに、
初めて、その存在がクローズアップされるからです。
しかし、主張が物別れになった場合、
こうした法律の存在感が大きくなります。
ですから、
民法、商法は私たちにとって大事な法律です。
しかし、税理士は、税務の専門家であって、
こうした法律は守備範囲ではありません。
それが、時々、問題を起こすことがあるのです。
この問題もそうしたケースでした。
もし、ご自分の生活感覚と税務の主張に
乖離がある場合、
このように民法や商法から考えてみてください。
自分の違和感が正しいという証明になることもありますから・・。
セカンドオピニオン
当社の活動の一部が、
日本経済新聞(平成22年7月3日)に紹介されました。
紹介されたのは、税務セカンドオピニオン・サービスの
『プライベート・コンセント』です。
当社が、このセカンドオピニオン・サービスをはじめた
2005年は、まだ、“セカンドオピニオン”という言葉は
一般的ではなく、ネーミングなどに苦労をした記憶があります。
今となっては、“セカンドオピニオン”という言葉を
素直に使えば良いわけですが、
当時は、この言葉は目立たない程度に使いました。
当社が、このサービスを開始すると、
追随者は、半年~1年ほどで現れました。
参入障壁が、ほぼ、ゼロのサービスですから、
追随者が現れるのは、当たり前のことですが、
私たちが、業界動向から疎遠になっているうちに、
インターネット上では税務セカンドオピニオン・サービスを
行う税理士サイトが雨後の竹の子のように増えたようです。
医療の世界から現れた“セカンドオピニオン”という言葉は、
今では、あらゆる業界で使われるようになりました。
“アウトレット”と並ぶ
21世紀以後に出現したヒットワードの一つと言っても良いでしょう。
“専門家”という言葉には、
“セカンドオピニオン”という言葉がセット。・・という時代に
なりました。
しかし、これは当然のことです。
私たちの社内でも、専門家同士が対立する意見を戦わせる場面は、毎日のようにあります。
それだけ、時代は複雑になり、一人の専門家の意見だけで
どうにかなる時代ではなくなっているのです。
さらに、肩書きだけが“専門家”という人も多くいます。
私たちは、お客さまを通して、そういう人たちにたくさん出会ってきました(間接的に)。
そして、そうした“専門家”という人たちは、
驚くようなアドバイスをしているのです。
ある若い税理士は、
私たちのセミナーに参加したお客様の
「キャッシュフロー計算書を作ってください」
の依頼に、
「あれはすぐには作れないものです」
と答えたそうです。
当社の新卒が10分くらいで作るものを
“すぐには作れない”というのは、
どういうことなのかと驚いた記憶もあります。
理想は、
”完璧な専門家”に出会うことです。
しかし、そんなことはあり得ません。
世の中が複雑になる。
試験だけで専門家が製造される。
この2つの背景を客観的に見るだけで、
“完璧な専門家”などあり得ないことが
わかります。
だから、
当社は、社内での意見を戦わせるように
なっています。
そして、
社外においても、
プロとしての意見を
多くの方々に利用いただきたいと考えています。
今日も、
顧問税理士さんが考えた相続対策に対して、
異論を主張し、まったく違うスキームを提案しました。
お客様には、2つの意見をよく吟味し
良かれと思うものを選んでいただけると思います。
八百屋で、大根を選ぶことと
それほど変わらない状況に持ってこれた時、
本当の専門サービスを受けられることになります。
回りくどいけれど仕方がありません。
続、なぜ税理士は必要なのか?
私は以前にこんな経験をしたことがあります。
ある零細企業の社長が顧問契約のご依頼でいらっしゃいました。
私 「本日はどのようなご相談ですか?」
社長 「顧問をお願いしたいんですが。」
私 「それはありがとうございます。」
私 「どなたかのご紹介ですか?」
社長 「いえね、銀行から税理士さんに相談してみてはどうか?と言われまして・・」
少し訳ありのようです・・・
話を聞いてみると,借入れの相談で銀行に行ったところ
決算書と申告書の提出を求められたそうです。
社長が決算書と申告書を提出したところこの決算書では融資できないと言われ、
税理士に相談してみるように勧められたとのことでした。
その社長は,以前からご自分でワープロで決算書を作り、その決算書を持って税務署に行き職員に聞きながら手書きで申告書を書いて提出していたそうです。
私はその決算書と申告書を見せていただきました。
ワープロで作った行間が間延びした表に、それらしい勘定科目と金額が入力してありました。
はっきり言ってひどい決算書です。
これがテストなら『10点』くらいでしょう。
貸借対照表は、前年度からの繰越額を無視した財産ベース。
損益計算書の売上、費用は入出金ベース。
申告書も当然でたらめです。
対応した税務署の職員も職員です。
前回、わたしたちが税務署に提出する申告書は『確定決算主義』という決まりを前提として作成されなければならないという話をしました。
それは株主総会で承認された決算書にもとづき申告書を作成しなければならないということです。
しかし、この確定決算主義には大切な大前提があります。
それは、『会社法』です。
会社法とは、すべての会社が従わなければいけない法律です。
会社法では会社が行う会計について次のように規程しています。
『会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。』
つまり、確定決算主義だからといってでたらめな決算書までもが認められるというものではありません。
私は前回、自主申告するのも一つの方法だとお話しました。
しかし、それは一般的な会計処理の基本が守られていることが大前提です。
何でもかんでも出せばいいというものではありません。
その結果、必要な時に、必要な資金を銀行から借りられなくなってしまうこともあります。
しかし,私はその社長のやってこられたことが間違っていたとは思いません。
ただ、その社長には相談相手がいなかった。
わたしたち税理士は申告書を作成するだけが仕事ではありません。
日常の経理上の疑問や、決算処理の相談に応じるのもわたしたちの大切な仕事です。
わたしたちエー・アンド・パートナーズ税理士法人では、低料金で経理周りの相談にお答えする『財務プライベートコンセント』サービスを行っております。
次の方々に最適なサービスです。
1.新規開業で顧問税理士を頼むまでもないとお考えの方
2.自主申告で毎年悩まれている方、、
3.顧問税理士以外の専門家の意見が欲しい方
上記の方々は、是非一度
『財務プライベートコンセント』サービスのご利用をご検討ください。
Japan is No.1
世界において、日本が1番のものを探してみます。
インターネットで治安 ランキングを検索。
イギリス経済紙エコノミストが発表している『世界平和度指数(2010年)』によると、1位はニュージーランド、2位がアイスランドで、日本は3位にランキングされています。
日本には、銃規制があり、諸外国に比べて、移民・外国人が少ない。
また、貧富の差が他国に比べて、それほど激しくない、といったような理由から、日本の治安の良さがあるわけですが、それでも1位ではないのです。
(そう考えると、北■鮮が、ダントツ1位のような気が・・・、実際は139位)
科学技術力はどうでしょうか?
総務省の統計によると、
研究者の数は、アメリカ、中国、に次ぐ3位(総人口が随分違いますけどね)
国内研究費でも、アメリカが1位で、日本が2位となっています。
・・・これも1位ではない。
あっ、・・・ついに見つけました、日本がNo.1、ただしアイロニーなNo.1。
・・・法人税率。
日本の法人税率は約40%、先進諸国の中では最も高いのです。
参考までに、各国の法人税率は次のとおりです。
アメリカ 39%
フランス 33%
ドイツ 29%
イギリス 28%
中国 25%
韓国 24%
ロシア 20%
香港 16%
参考:JETRO
法人税率が高いことによるデメリットはいくつもありますが、
■給料や各種経費への配分が少なくなってしまうため景気が悪くなる
■ジャパンマネーが軽課税国へ流れ、また、外国企業の対日投資が減る
といったあたりが主なところです。
しかしながら、本当に法人税率を下げてもいいのでしょうか?
日本は収入よりも支出が多い国、その差額を借金で工面している、というのが現状です。
「ただでさえ少ない収入をさらに減らす?日本の財政状況はどうなるの?」といった声が聞こえてきそうです。
ここで登場する考え方が『法人税パラドックス』です。
学者やエコノミストの多くが唱えています。
『法人税パラドックス』とは、
■税率を下げることと、租税特別措置法(スポット的な減税措置)の見直しはセットで行われ、それ相当の減税措置が廃止になる。
■個人事業と法人との税バランスを考慮し、新規設立法人が増え、法人自体のパイが増える。
■税金が下がった分、設備投資や、労働分配に充てることができるため、景気の循環がよくなり、個々の法人の利益が増える。
といったようなロジックから、法人税率を下げても、法人税による税収は減らない、という考え方です。
内閣が6月に発表した『新成長戦略』においても、法人税の減税は謳われていますし、平成23年度税制改正に向けた各業界からの要望でも、法人税率の引き下げは最初に掲げられています。
また、帝国データバンクが7月に行った『法人税率に対する企業の意識調査』においても、7割超の企業が「引き下げるべき!」と答えています。(当事者なのだから・・・、それはそうでしょう(笑))
それらを踏まえると、法人税率の引き下げは、平成23年度税制改正の目玉となることは間違いありません。
さきほど『法人税パラドックス』の1つの要因として掲げた、法人の新規設立について、当社でも会社設立サポートプランをご用意しております。
新規設立を検討されている方はお気軽にご相談ください。・・・と言いたいところですが、法人税率が引き下げられることを見込んでの、安易な設立目的の方はご遠慮ください。
HP上でも詳しく触れていますが、法人の廃業数は開業数の約2倍、当社も現場を通して事業の厳しさをイヤというほど見てきました・・・。
なかには、事業としての成立が困難と判断し、会社設立自体を考え直すようお伝えしたケースもございます・・・。
会社の設立自体が目的なのではなく、本気で事業の成功を考えている方は是非ともご相談下さい。
当社も本気でサポートいたします。
キューバの「15分」
いろいろなことがあって、約4年もかかってしまった本が、ついに出版されました。
原稿のやり取りは、3回も繰り返し、その都度に中身も大幅に変わるという大変な本になりました(著者のワガママでしかありませんが・・)。
本のタイトルは、『実学 中小企業のパーフェクト会計』です。
この本のあとがきは、以前、どこかで
転載させていただいたことがありますが、
この本の根幹になる考えが入っていますので、
一部を読んでいただこうと思います。
******************************
(あとがき)
この本の執筆が終わった直後に、キューバを旅する機会を得ました。
現代史における有名な事件やブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブの成功などたくさんのコンテキストを想起させるこの国は、単なる南国の島を超えた魅力的なところでした。
キューバの旅の最中に、馬車でヘミングウェーの別荘へ行くことになりました。タクシーで20分くらいと聞き、突然行くことに決めた予定外の行動でしたが、タクシーで目的地に向かおうとタクシー乗り場に行くと、馬車でも40分で行けると聞き、馬車で目的地に向かうことにしました。
しかし、馬車に揺られて1時間。まったく目的地らしきところにも着きません。ハバナを午前中に立たなければならないことになっていた私たちは焦りました。「後、どれくらいで着くのか?」と質問すると、馬車の運転手は「15分」と回答しました。すでに乗ってしまった馬車です。15分の我慢は仕方がないと諦めました。
ところが、15分後に同じ質問をすると、再び「15分」との回答・・。日本ではあり得ない話ですが、海外旅行では誰もが経験するであろうアクシデントの一つだと思います。
南の島の社会主義国では、私たちの国と比べると時間がゆっくり流れています。しかし、その南国の景色は、日本にもある。私はそう思います。
中小企業の経営者の中には、自社のROAや労働分配率、ひどいケースでは自社の売上げや利益さえわからないという人がいます。こうした景色と「15分」を言い続ける馬車の運転手に違いはあるでしょうか。
違うことがあるとすれば、キューバでは、「15分」と言い続けることができても、日本ではそれが無理だということくらいでしょう。
ヘミングウェーの別荘に行った私たちは、結局、別荘を見学する時間がなく、早々と再び馬車で戻りました。現地でタクシーを捕まえることができず、再び1時間半ほどの時間を要するしかありませんでした。
往復40分の予定時間は約3時間と4.5倍の時間に化けました。そして、ホテルのチェックアウトの最終時間に遅れ、タクシーの待ち合わせ時間にも遅れることになりました。
本書は、中小企業や自営業者のために実務的な会計の本を作ろうという考えから制作されました。本書内で紹介している数値管理は、実際に、私が主宰するエーアンド・パートナーズ税理士法人にて中小企業経営者の方々に提供させていただいているものです。
・・・・・・・・・・・・・・・
******************************
キューバーでは必要のない「15分」の概念は、
日本では絶対に必要なものです。
その「15分」の概念を
たくさん、ねじ込んだ本が『実学 アクション会計』です。
出版になりましたら、ぜひともご購入ください。
中小企業会計のバイブル本ですので、価格は少々高いですが、お役に立つと思います。
値下げという圧力
皆さんの会社は、“値下げ”という圧力に悩まれていないですか?
競合会社との値引き合戦
デフレという世間的な値下げの波
取引業者からの単価引き下げのお願い etc.
値下げ圧力に抵抗するのはかなり難しいはずです。
仮に、この圧力を無視すれば、売上が“ごそっと”消える場合もあります。
ですから、ほとんどの会社は、値下げを受け入れざるを得えません。
これを跳ね返す事が出来るのは、競合がいないブルーオーシャンをひた走る企業か、一時的な売上減少をものともしない優良企業だけ。
結局、値下げ圧力に屈するしかない企業は、売上の減少に拍車が掛ります。
だからこそ、コストを下げない限りは生き残れない・・・。
「リストラなら、出来る事は全てやっているよ」
皆さん、そうお考えのはず。
ですが、いわゆるリストラではなく、本来の意味の『リストラクチャリング』を実行するのが本来取るべき手段になります。
つまり、ビジネスモデルの『再構築』。
そこで、今回は税理士業界で起っている値下げ圧力のお話をします。
最近、お客様からの新規問い合わせ理由で一番多いのが、“税理士報酬を減らしたい”です。
なぜ、税理士報酬を減らしたいのか?
「売上が下がって利益も出ない。
そんな状況で、適切なアドバイスもしてくれない税理士に
この顧問料は高いと思う」
確かに、皆さんのお話を聞く限り、税理士の仕事と報酬が一致していません。
これを適正な水準にしようと、比較的ムダだと思われがちな税理士報酬に値下げの圧力が掛っています。
この値下げ圧力に対してこの業界が取っている対応は、報酬の引下げと引き換えに、仕事の質量を単純に引下げるという方法です。
ここに、お客様の満足度は考慮されません。
お客様の側も、報酬が下がるなら構わないというような姿勢です。
しかし、一度そのお客様との付き合い方を変えた場合、仮にお客様側の状況が変化しても、税理士事務所側のやり方が変わるのは中々難しい・・・。
つまり、柔軟な対応が出来る税理士事務所は数少ないのが現状です。
そして、その不幸な関係のまま付き合いが浅くなり、数年後に税理士が変わるという流れです。
こうなると、柔軟な対応を考える税理士事務所は、やり方を変え、コストを下げ、お客様の満足度を満たしつつ、顧問料を“相対的に”下げる方法を提案するしかありません。
それこそ、ビジネスモデルのリストラクチャリングが求められます。
ちなみに、常に柔軟でありたいと考えている当社では、下記のシステムを導入しました。
http://www.isllight.jp/jp/
簡単に言えば、パソコンの遠隔サポートシステムです。
導入理由は、お客様への訪問時間・回数の短縮による時間効率を高めつつも、コミュニケーションレベルは下げないためのツールとして有効と考えたからです。
税理士事務所のコスト構造は、分析するまでもなく人件費比率が圧倒的に高い。
また、労働集約的なビジネスのため、どのお客様にどのくらいの時間を割くかの管理が重要になってきます。
そのため、時間効率を高める事が、報酬を相対的に下げるための必要条件となります。
このようなシステムを用いれば、事務所内にいながらお客様の会計データ等を直接サポートする事が出来ます。
さらに、メールや電話では上手く伝わらないお話の時に、資料をPDFでメールしつつ、その資料を画面共有で“ペンを入れながら”説明も出来ます。
近年、会計ソフトのWEB化の導入期でもあり、効率性を重視する税理士事務所が積極的に導入を進めています。
ただ、効率性だけを考えたモデルですと、LIVE感のない機械的な仕事になりがちなので、それを嫌がるお客様もいらっしゃいます。
当然、税理士事務所側の仕事の精度も落ちます。
当社は両方を扱っていますが、今のところお客様の反応が良いのが、会話しながらお客様のパソコン画面を共有する遠隔サポートシステムでした。
私個人としては、お客様の現場に立つという事を重視しているので、遠方でも訪問して仕事をしたいという気持ちもあります。
しかし、その方法だけにこだわっていては、新しいモデルを取り入れる事が出来ません。
結局、当社も『税理士事務所のコスト構造』からどのように柔軟に脱却するかを考えながら、リストラクチャリングを模索しています。
この模索が、新しいビジネスモデルの創造につながると考えているからです。
そういう意味では、近年のような値下げの圧力をビジネスモデル変更のシグナルと捉えている企業は、次の圧力の波を乗り切れるかもしれませんね。
いずれにしても、値下げの圧力に為すがままの状態では、潰れゆくのが見えていますから・・・。